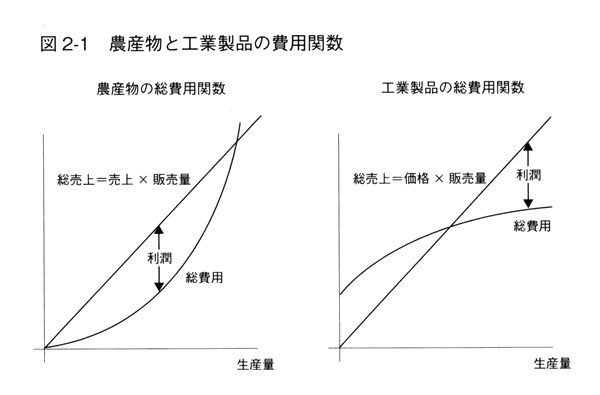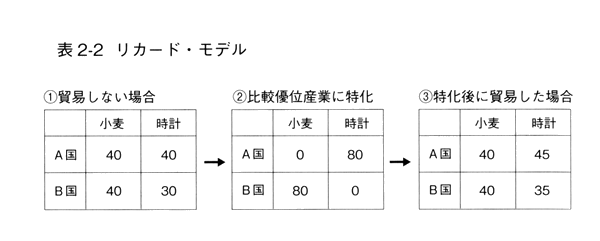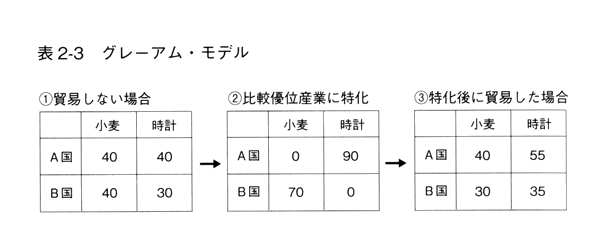自由貿易によって貿易する双方の国に利益が発生するというリカードのモデル世界は、現実世界からほど遠い。そこで本章ではリカード・モデルの非現実的部分をいくつか現実的なものに置き換えていきたい。そうするだけでリカードの世界とは全く違った世界が現れる。本章で取り上げる主な論点は以下の通りである。
あらかじめ貿易自由化問題に関する私のスタンスを述べておく。百歩譲って工業製品の貿易自由化は許容したとしても(それも実際には問題が多い)、農産物(とくに穀物)や天然資源には自由貿易の原理に適さないあまりにも多くの理由がある。それゆえ各国・各地域は持続可能な資源管理を行うための諸規制を設けるべきであるし、農業を保護し、食料自給を維持する権利が認められるべきある。 工業製品に関しても、自由化を許容するためには労働基準や最低賃金、環境基準の国際的な適正化、タックスヘイブンを規制し、法人税率も国際基準で適正化して政府が十分な所得再分配機能を果たし得る税率とし、さらに国際的な独占を禁止するなどの諸条件が必要であろう。 現状ではその条件が整っていないので認められない。また、たとえ工業製品に関して上記の諸条件が満たされたとしても、世界規模で総需要が収縮した不況時に大量の失業者が発生した際、為替レートが急激に変動した際、貿易不均衡が急拡大した際などにおいては、セーフガードとしての関税措置はやはり必要である。 関税率の水準は、国際協調を保ちながら、経常収支の均衡を保つという観点から決めるべきであろう。大量の失業者を出さないという大義は、特定の企業の私的利益に優先されるべきなのだ。
自由貿易を擁護するデイヴィッド・リカード(1772〜1823)の比較生産費説は、産業革命を成し遂げたイギリスが、その工業力による余剰生産物のはけ口を外国に探し求めていた1817年に提唱された。リカードの理論は、多くの非現実的な仮定の上に展開され、非現実的な結論が導かれている。数ある非現実的仮定の中からあえて一つ選べと言われたら、私は生産費用不変の仮定を最大の問題として取り上げたい。 リカードの理論は、生産規模の拡大や学習の効果や技術革新などによる動学的な生産費用の低下という現象を考慮に入れていない静学理論である。ドイツのフリードリッヒ・リスト(1789〜1846)が1841年に著した『経済学の国民的体系』の中で問題にしたのもこの点である。すなわち、短期的に国際競争力がないと思われる初期段階の産業(=幼稚産業)であっても、国が関税によって外国製品の流入を抑制しながら、技術力を開発・育成し、製造能力を高めていけば、生産費用は低下し、将来的には十分な競争力を持つように成長する。 アメリカの経済学者フランク・グレーアム(1890〜1949)は1923年、農業と工業の生産費用の動学的変化を組み込んだモデルで保護貿易の理論を提唱した。リカードが農業と工業とを問わず貿易する双方の国に貿易利益が発生すると主張したのに対し、グレーアムは、農業に特化するのは不利であり、保護関税を駆使して工業に特化する必要性を論証した。 工業は、生産量の拡大によって単位生産費用が減少していく性質(収穫逓増と呼ばれる)を持つのに対し、農業はその逆で単位生産費用が増大していく(収穫逓減と呼ばれる)。貿易をして生産量が拡大していった際、工業は単位生産費用が逓減して利益は増大していくのに対し、農業に特化すると利益が減少していく。
図2-1は、農産物と工業製品の生産量をそれぞれ拡大していくにつれ、生産費用がどう変化していくのかを見たものである。図の前提として、横軸はその財の生産量を取った。縦軸には生産された財が全て売れた場合の総売上と、その生産に要した総費用を取った。単位は金額である。生産者の利潤は、「利潤=総売上−総費用」であるから、総売上曲線から総費用曲線を引いたものになる。 総売上に関しては、話を簡単にするため、財の価格を一定とした。価格が一定であれば、「総売上=価格×個数」であるから、総売上の関数は価格に個数を掛けた単純な正比例のグラフになる。 総費用の関数は、産業の性質によって形状が大きく異なる。農産物と工業製品ではその形状はどう異なるであろうか。農産物は、太陽光と水と二酸化炭素の賦存量に規定された光合成の能力以上には生産不可能である。土地に限りがあれば、どれだけ機械や化学肥料などを追加的に投入しても、投入の増加に見合うだけの産出の増加は得られない。投入の増加に比して、産出の増加は小さくなり、いずれは限界に達する。工業の場合、規模の経済効果が働き、大規模になればなるほど製品一単位当たりに要する生産コストが減少し、結果として利潤は増大する。 農産物では、一単位追加的に生産する費用(経済学では限界生産費用と呼ばれる)は逓増していくのに対し、工業製品では逆に逓減していく。つまり、農業は収穫逓減(=限界費用逓増)、工業は収穫逓増(=限界費用逓減)の傾向を示す。 おそらく経済学部出身以外の大方の読者は、この図を見て何ら違和感を覚えないだろう。しかし経済学部出身者は「教科書に書いてあることとは違う。おかしいのではないか」と主張するかも知れない。そう考えた経済学部出身者は、教育を通して洗脳された結果である。 工業製品が収穫逓増の傾向を示すのに対し、農産物は収穫逓減の傾向を示すという事実は、古くはアルフレッド・マーシャル(1842〜1924)が「経済学原理」の中で詳しく論じている。マーシャルは次のように述べている。 生産において自然の果たす役割は収穫逓減の傾向を示し、同じく人間の果たす役割は収穫逓増の傾向を示すといってよいだろう。収穫逓増の法則はつぎのように述べることができる──労働と資本の増大は、それらの果す仕事の能率を増大させる、改善された組織に導かれると。 その後の新古典派経済学は、マーシャルが論じた収穫逓増の世界を忘れ去ってしまったようであった。大学生が習うミクロ経済学の教科書は一般的に、収穫一定または収穫が逓減するような費用関数しか扱わない。収穫が逓増するような形状では、図を見れば明らかなように、利潤が最大化される点が存在しないので、数学的な均衡解が得られない。 現実には収穫逓増のケースはたくさんある。端的な例がソフトウェア産業であろう。ソフトウェア製品の開発には大きな費用を必要とするが、ひとたび開発されてしまえばあとはコピーするだけなので、追加的な生産コストはほとんどかからない。 経済学が収穫逓増を認めると、市場経済からは「均衡」が消え去り、市場原理を礼賛する人々にとっては都合が悪いことになる。そこで臭いものにフタをしてしまって教えないのである。 農産物の費用関数 図を見れば分かる通り、農産物の場合には総売上から総費用を引いた利潤が最大化される「利潤最大点」が存在することになる。総費用曲線の接線の傾きが価格と等しくなったとき、利潤は最大化される。総費用曲線の接線とは、その生産量において追加的に一単位生産するのに必要な費用である。利潤最大点を超えると、追加的に一単位生産するのに必要な費用が、製品の価格を上回ってしまうので、それ以上生産すれば利潤は減っていってしまう。こうした特質は収穫逓減と呼ばれる。 経済学では、「追加的に一単位生産するのに必要な費用」のことを「限界費用」と呼んでいる。「限界」という言葉を使った途端に、経済学部出身者以外の人々は煙に巻かれて分からなくなってしまう。実際、「限界」とは「わけの分からない訳語」と言ってよい。限界という言葉の使い方が、本来の日本語の意味と異なるので、日常一語に慣れ親しんだ人々は、経済学者が何を言っているのか分からなくなる。 経済学者が不可思議な言葉を使うのは、神話を防衛するためには有効に機能する。「限界」という不適切な専門用語を用いて一般の人々を煙に巻くことによって、一般の人々が市場原理主義に対する疑義を申し立て、新古典派ムラの秩序を脅かすのを防止する効果があるからだ。 微積分を学習した人々にとっては、経済学における「限界」とは、要するに微分値のことであるといった方が理解しやすいだろう。 もちろん最終的には生産量は決まってくるのだが、これは需要側の制約によって売れ残りが発生することから生産を止めるのであって、生産側の都合で生産量を決めているわけではない。 たしかに農産物のような収穫逓減の条件では、価格が所与であればそれに合わせて利潤が最大化されるように生産量が決まってくる。生産者は、価格に応じて利潤が最大化されるような供給量を選択するかもしれない。この場合、供給曲線が描けることになる。しかし工業製品はそうはいかない。収穫逓増の現実世界では利潤最大点などないから、価格が決まっても「売りたい量」は一点には決まらない。その場合、価格を独立変数として供給量を従属変数とする供給関数というものは決まらないのである。 さて、収穫逓増という状況下で何が発生するだろうか。 製造業メーカーは、国境の壁が取っ払われて世界が単一市場となるグローバル経済を強く望むようになる。売れば売るほど利潤が増える世界では、国境など邪魔くさい存在でしかない。よって、国際競争力のある日本経団連傘下の諸企業は、強く関税の撤廃とグローバルスタンダードによる世界市場の統一を望むようになる。彼らの気持ちはよくわかる。1000万人の市場で勝負して勝ち残った企業は、次には1億人の市場を相手にしたくなり、その次には10億人の市場を望む。彼らの欲望が果てることはない。これは工業製品の収穫逓増という性格に規定されているのである。 売れば売るだけ利潤が増えるという収穫逓増の世界におけるグローバル大競争の果てに出現するのは、グローバル独占企業による世界市場の独占あるいは寡占支配である。この場合、最終的には競争もなくなり、価格面での消費者利益も吹き飛んでいく。収穫逓増の性格が強ければ強いほど、グローバル独占は成立しやすくなる。先に述べたようにソフトウェア産業などは、ひとたび製品を開発してしまえば、それをコピーするのに追加コストなどほとんどかからない究極的な収穫逓増産業といえる。それゆえマイクロソフト社の世界独占が容易に成立したのである。 それに対して、収穫逓減産業である農業の場合、グローバルな単一市場など必要とされない。必要以上の規模拡大は逆に利潤を低下させるという農業の場合は、節度をもって生産量を抑制し、最適な量を地域の消費者に提供していくという、本来的に地産地消型の産業である。収穫逓減産業の農業には、10億人単位のグローバル世界市場など不要なのである。 図2-1を見れば、収穫逓増産業の工業に特化し輸出を拡大した場合に利益は大きくなっても、収穫逓減の農業に特化した場合、輸出を拡大したところで利益が大きくなることはないとが分かるであろう。農産物の場合、供給面の収穫逓減の制約に加えて、需要面でも市場が飽和しやすく、従って価格が下落しやすいという制約がある。 農業に競争力があり工業に競争力のないアメリカ合州国の場合、農産物をいくら輸出しても貿易赤字は増え続けている。輸出すればするほど、農業に投入する補助金の額も増えてしまい、国民負担を増やし、財政を逼迫させる要因になっている。アメリカのアグリビジネスが農産物貿易の自由化を主張するのは、連邦政府の財政支出の中から多大な補助金を得られるという、利権目的の非市場的な要因によるところが大きいのであろう。 リカードの比較生産費説 まずはリカードのモデル世界を確認しておく。A国とB国は、それぞれ2単位ずつの労働力が賦存し、1単位ずつの労働を振り分けて小麦と時計を生産しているものとする。A国では1単位の労働で小麦40単位、同じく1単位の労働で時計40単位を生産する。B国は小麦40単位、時計30単位を生産する。リカードの比較優位論モデルでは、相対的な得意分野に生産を特化した方がよいとする。この場合、A 国は時計に特化し、B国は小麦に特化すべきということになる。 リカードの静学的な説明によれば、A 国は時計にB 国は小麦に特化して生産を行うと、A 国では時計80単位、B国では小麦80単位の生産が可能になる。その後、A国とB国が貿易をすると双方の国に貿易利益が発生する。 両国が貿易する際、小麦と時計の交換比率は必ずしも自明ではないが、貿易前における小麦の全生産量80単位と時計の70単位が同じ価値として取引されると仮定すれば、交換比率は小麦40に対し時計35となる。B国が小麦40単位をA国に輸出すると35単位の時計を輸入可能である。 両財の相対価格が変化しても、小麦40単位に対し時計が40から30単位交換される範囲であれば、双方の国に貿易利益が発生する。 工業に収穫逓増、農業に収穫逓減を導入した場合 リカード・モデルは生産要素を労働のみに限定するという、いわゆる労働価値説に基づいている。より一般化して、労働以外にも資本や土地といった、複数の生産要素を考慮に入れた場合のモデルがヘクシャー=オリーンの貿易モデルである。生産要素が複数あるヘクシャー=オリーンのモデルの場合、生産要素の投入量をそれぞれn倍にしたとき、その製品の産出量がn倍になれば収穫一定、n倍より大きくなれば収穫逓増、少なくなれば収穫逓減と定義される。 工業の場合、「労働」と「資本」というこつの生産要素を考えればよい。農業の場合、「労働」と「資本」に「土地」も加えた三つの生産要素を考慮せねばならないという点で、より複雑である。 いま小麦に特化したB国が、同じ面積の農地に対して労働投入量を2倍に増やしたとしよう。2倍の産出が得られないことは明らかであろう。同一面積の土地からは光合成の限界という、自然が規定する最大値を超えて生産することなどできないからだ。 では、労働と資本のみならず農地も2倍にしたら、産出量は2倍になるだろうか? これも多くの場合は不可能である。というのも、貿易前にB国が40単位の小麦を生産していたのは、国内でも肥沃で土壌条件の良い優良地であったはずだからである。小麦に特化して農地を2倍に拡大したとして、追加的な土地は、それまでは農地利用されていなかった山間の傾斜地や日射量の低い地域や少雨地域など、自然条件の点で相対的な劣等地のはずである。肥沃な土地で40生産できていたとして、同じ面積の劣等地に生産を拡大しても40を生産できないことは明らかであろう。30しか生産できないかも知れない。 農業の場合、労働、資本というこつの生産要素に加え、土地という生産要素の寄与度が大きく、土地生産性は土壌肥沃度や日射量など天与の自然条件に大きく規定され、さらに光合成の限界という人間の力では越えられない上限がある。これは競争の前提条件として人間の努力では如何ともし難い部分である。 小麦と時計の交換比率が、小麦40に対して時計30のままであれば、B国は貿易後に小麦30と時計35しか得られない。小麦は10単位減り、時計は5単位増えるが、時計5単位の価値は小麦5.7単位分しかないので、取得する価値の総体としてB国は貿易前よりも純粋に損失を被るのである。それに対し、A国は時計を55単位取得するので、大きな貿易利益が得られる。 このように、収穫逓増産業である工業製品に特化すれば利益が得られるが、収穫逓減産業である農産物に特化しでも利益は得られず、貿易前より困窮することになってしまう。また、特化した後に突然に小麦の相対価格が高騰する場合など、B国もA国も共に損失を被る可能性も発生する。これは穀物供給量が逼迫すると考えられる今後の現実世界において懸念される事態である。 学習の効果による収穫逓増を組み込んだ場合ここでリカードが考慮しないもう一つの収穫逓増の現実を導入してみよう。 工業製品に関しては、生産要素の投入量を増やす「規模の拡大」によって逓増するという側面の他に、技術の進歩や学習の効果という時間の経過に依存する収穫逓増も存在する。リカードの議論は、技術進歩や学習効果によって生産費用が低減するという経済発展の動学も無視しているのである。 B国では元来、労働1単位の投入で時計30単位しか生産できず、A国と比較して競争力がなかった。ここでB国は、後発国であるが故に技術力が追い付いていなかったのだとすれば、政府が関税によって保護してでも、戦略的に技術力を高めていけば、やがてA国の生産性に追いつくかも知れない。 B国は、将来的にA 国と同じ40の労働生産性を獲得できるのであれば、B 国の被る貿易損失は数字以上である。貿易しなければB国は、潜在的に小麦40 、時計40得られたはずであったのに、貿易したことによって30、35しか得られなくなるからである。 ゆえに後発工業国は、技術的に追いつくまでは保護関税等を駆使して安価な工業製品の流入を抑え、先進水準に追いついた段階で関税を引き下げていけばよいことになる。これがフリードリッヒ・リストの提唱した幼稚産業保護論である。実際にドイツ、アメリカ、日本等の後発工業国が先進技術にキャッチアップする際に、普遍的に採用した戦略である。
私は、双方の国が得をするウィン-ウィン関係になるような貿易をすべきであって、貿易パートナーを困窮化させるような攻撃的輸出はすべきでないと考える。悲しむべき事実だが、貿易は所詮勝つか負けるかの戦争であり、日本はTPP に参加して貿易戦争で勝利すべきだといった勇ましい意見も多い。千歩譲って、近隣諸国を窮乏化させてでも自国のみは貿易利益を上げようという、「国家の品格」に全く欠ける議論を認めたとしても、なおかつ収穫逓増の工業製品を世界市場に輸出すれば幸せになるかと問えば、それもリーマン・ショック以降の世界経済の情勢下においては全くの誤りである。 上述のリカードの空想的なモデル世界の議論に、収穫逓増と収穫逓減を導入することにより、より現実的になっている。しかしながら、現実世界と照らし合わせると、まだおかしい点がいくつもある。お分かりだろうか? 致命的におかしいのは、A国は貿易の結果、時計を55単位取得するが、それが国内で全て需要されると想定されている点である。もともとA国では時計が40単位しか需要されていないのだから、55単位全て売れるとは限らない。 じつはリカード・モデルには需要という概念がない。リカードの理論は「供給したものは必ず需要される」という命題(「セーの法則」と呼ばれる)を暗黙の前提にしているのだ。現実には、A国で生産した工業製品が全て需要されない場合、A国は深刻な失業問題に直面することになる。 かりに時計に対する需要は40から45単位にしか増えず、残り10単位は売れ残ったとしよう。その場合、A 国は深刻な失業に直面することになる。90単位の時計を生産したA 国で、10単位売れ残るとすれば、就業者の11.1%(10/ 90) が失業に追い込まれてしまう。この場合、GDP は当初の小麦40と時計40から、時計80(90−10) の売上になり、時計換算した価値では75から80になる。GDP レベルでは6.7%の経済成長になる。しかし、その代償として失業率が0から11%へと増加することになる。 はたして6.7%の経済成長と引き換えに11%の失業率上昇を甘受せよと言われたら、人々は受け入れられるだろうか? 株式投資などをする人々にとってはGDP が増える方が株価の上昇につながるのでうれしいかもしれないが、大方の人々はGDP よりも完全雇用を選ぶのではないだろうか。社会の安定の方が経済成長よりも重要だからだ。加えていえば、国内に農地と工場の双方があった多様性のある景観から、農地が消えて工場だけになるという殺風景さに耐えられないという人々が多いだろう。 工業に特化してかつ失業問題が発生しないためには、国内外で当該工業製品に対する需要が伸び続けなければならない。工業に特化して経済成長と低失業率の双方を実現するためには、世界規模での総需要が伸び続けるという条件も必要なのである。 リーマン・ショック以降の現実世界 百歩譲って、世界規模で総需要が増大するという条件下において、貿易を自由化して工業製品の輸出を伸ばすという利己的な戦略が国家的に有益であったとしても、世界の総需要が減少する現在の世界においてTPP のような原理主義的な域内貿易自由化を叫ぶのは、工業国の国家的利益に立脚したとしても、なおかつ誤っているのである。 2000年代の日本においては、輸出の増加により確かにGDP は成長していたが、失業率は高止まりしたまま雇用状況は改善されなかった。いわんや世界的需要不足状態にあるリーマン・ショック以後の世界においては、この状況は一層ひどくなる。TPP に参加して製造業部門での国際競争力を高めたとしても、失業は増え、賃金も下落していくという現実に直面する。その結果、世界総需要の衰退に拍車をかけてしまうことになる。 つまり世界総需要の衰退下において追加的に貿易を自由化しようとするのは愚の骨頂なのである。かかる情勢下において、健全な世界貿易を維持したいのであれば、貿易自由化交渉など棚上げにした上で、雇用の改善を図り、内需を維持するのが正しい政策となる。世界全体の総需要が維持されれば貿易も円滑に展開され得るが、過激な貿易自由化によって各国の失業者が増加し、賃金水準も低下していけば、逆説的であるが、かえって世界経済全体の総需要が収縮し、貿易も衰退していくからである。繰り返すが、総需要が減衰する世界における過激な貿易自由化は、逆説的に世界貿易を衰退させるという現象を生み出すのだ。‥‥
|